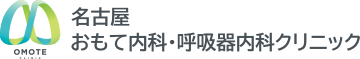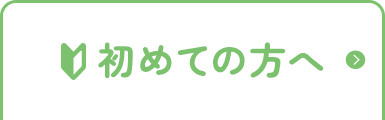健診や人間ドックで「胸のレントゲンに異常がある」と言われたことはありませんか?
「でも症状はないし、どうしたらいいの?」──そんな疑問に、呼吸器内科専門医がわかりやすく解説します。
下記のYOUTUBE動画と解説記事を参考にしてください。
✅ 異常陰影のよくある原因
✅ 二次検査(CT検査)の内容と流れ
✅ 費用や被曝リスク
不安を感じたときに、まず見ていただきたい動画です。
👉【YouTube】「健診レントゲンで異常を指摘された場合」
<目次>
① 健診で指摘される胸部レントゲン異常って何?
② 呼吸器内科での評価の流れ(初診〜追加検査まで)
③ 代表的な検査結果別の考えられる病気
④ 経過観察と“放置”の違い—再評価間隔の考え方
⑤ 放射線の被ばくに関して(大丈夫なの?)
⑥ よくある質問(Q&A)
⑦ 受診前に準備するもの(診療がスムーズになるチェックリスト)
⑧ 院長からのメッセージ
1. 健診で指摘される胸部レントゲン異常って何?
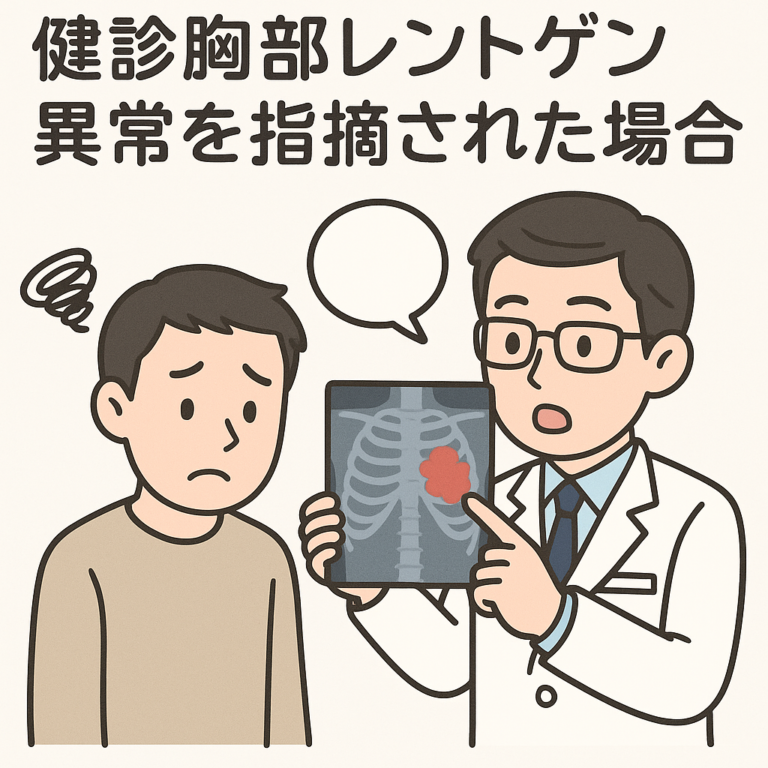
胸部レントゲン検査は「疑いを拾う検査」
胸部X線(レントゲン)はスクリーニング検査で、臓器が二次元に重なって投影されます。そのため実体が一つの病変とは限らず、血管や肋骨、横隔膜、乳頭影の重なりでも「異常影」と記載されることがあります。そのため健診の胸部レントゲン検査で異常を指摘され、胸部CTで精査を行っても異常はないことはしばしばあります。またこれは健診の胸部レントゲンでは、少しでも肺がんなどが疑わしい場合は異常と判定することが多いためです。
また近年では、AIによる自動判定で異常影と診断されることも増えてきています。
疑わしい影をレントゲンで拾って、胸部CTで精査を行います。
2. 呼吸器内科での評価の流れ(初診〜追加検査まで)
① 問診と身体診察
どのような異常を指摘されたか確認します。健診で異常を指摘されているため無症状で受診される方が多いですが、場合によっては症状・経過・薬剤歴をお聞きします。
② 胸部CT(必要に応じて低線量CT)
胸部CTでは、胸部レントゲン検査で見えなかった微小結節、辺縁のトゲ(スピクラ)、石灰化、空洞形成、リンパ節腫大、胸膜肥厚などを立体評価することができます。結節の大きさ・密度(充実/すりガラス)・形などを見て、悪性のものかどうか、すぐに追加検査が必要かどうかを判定します。
肺がんなどの悪性腫瘍を疑う場合は、総合病院へ紹介します。総合病院では、気管支鏡検査などの追加検査が必要となることがあります。
③ 血液検査
胸部CTでの検査の結果、非結核性抗酸菌症などの感染症が疑わしい場合は、血液検査や喀痰検査(一般細菌、抗酸菌検査)などを追加検査します。
3. 代表的な検査結果別の考えられる病気
① 結節影(粒状・丸い影)
結節影(けっせつえい)は、良性腫瘍(過誤腫など)、炎症性肉芽、肺がん、リンパ節腫大の投影、などで見られます。そのほかにも乳頭(乳首)が結節影のようにみえることがあります。
② 浸潤影(濃い白い影)
浸潤影(しんじゅんえい)は、細菌性肺炎、非定型肺炎、器質化肺炎などで見られます。健康診断を受けた際に、発熱や咳・痰などの症状があった場合、たまたま肺炎の状態であったということもあります。
③ 網状影・すりガラス影
網状影(もうじょうえい)やすりガラス影は、間質性肺炎・ウイルス性肺炎・心不全に伴う変化などで見られます。
④ 胸膜肥厚
胸膜(きょうまく)と呼ばれる肺を包む膜が、通常よりも厚い場合に指摘されます。多くの場合、肺尖部(肺の上の方)にあって問題ないものがほとんどですが、まれに肺がんや胸膜肺実質線維弾性症のことがあります。判定が「経過観察」となっている場合は問題ないですが、「要精査」となっている場合は必ず病院に受診しましょう。
4. 経過観察と“放置”の違い—再評価間隔の考え方
胸部CTを実施した結果、小さな結節影がみつかることがあります。この場合、悪性の可能性が高いと判断すると高次医療機関へ紹介します。悪性かどうかは、結節影の濃さ、辺縁(スピクラなど)・形状などをみて判断します。
良性の可能性が高く、ごく小さな影の場合は経過を見て増大してこないかどうか観察します。徐々に大きくなっていく場合、精密検査を行います。
「問題なさそうなので様子をみる」は放置ではなく、計画的に再評価を行っていきます。
5. 放射線被ばくに関して
各検査の被ばく量の目安(成人)は以下の通りです。
・胸部レントゲン(正面1枚):およそ 0.02〜0.05 mSv
・胸部CT(標準プロトコル):およそ 3〜7 mSv(装置や体格で変動)
・低線量胸部CT(肺がん検診・経過観察向け):およそ 1〜2 mSv
参考として、日本の自然放射線被ばく(宇宙から地球に降り注ぐ放射線量)は年間およそ 2 mSv 前後です。つまり標準的な胸部CT 1回 ≒ 1〜数年分の自然放射線に相当し、低線量CT 1回 ≒ 半年分程度が目安です。
放射線の被ばく線量が100ないし200ミリシーベルト(短時間1回)を超えたあたりから、被ばく線量が増えるに従ってがんで死亡するリスクが増えることが知られています。そのため胸部CTを1回撮影する分には、がんの発生リスクは非常に低いと考えてよいと思います。
6. よくある質問(Q&A)
Q1. 「異常影=がん」の確率は?
A. 結節の大きさ・辺縁・充実性、喫煙歴、年齢、増大速度で大きく変わります。石灰化や平滑辺縁、小型・不変なら良性の可能性が高くなります。一方不整形・スピクラ・増大は悪性(がんの)可能性が上がります。確率を机上で決めず、CT+経時的な比較・変化で判断します。
Q2. 「症状がないから大丈夫」?
A. 早期肺がんは無症状がよくあります。胸部レントゲンで偶然見つかることは珍しくありません。症状の有無だけで安心しないことが重要です。
Q3. 「経過観察=放置」?
A. いいえ。明確な基準に基づく再評価です。増大・性状変化が無いか、期限を決めて追跡します。
Q4. すぐにCTは必要?被ばくは?
A. 多くのケースでCTが最初の追加検査となります。最新装置では低線量で実施可能です。
Q5. 低線量だと見落としが増えない?
A. 目的を明確化し、結節評価などに適した条件を選べば、診断価値を保ちつつ線量低減が可能です。必要に応じて標準線量との使い分けを行います。
Q6. 結核の心配は?
A. 画像所見・曝露歴・症状で疑えば喀痰検査等を直ちに行います。必要時は感染対策を含めて対応します。
7. 受診前に準備するもの(診療がスムーズになるチェックリスト)
① 健診の読影レポート(「要精密検査」「経過観察」の記載を確認します)
② 画像データ(CD/USB):もし画像があれば持っていきましょう。可能なら過去数年分のX線やCTもあるとよいです。過去画像との比較が診断精度を上げます。
③ 症状メモ:発熱、咳、痰、血痰、息切れ、胸痛、体重減少などの症状が健診を受けたときにあったかどうかが重要です。
④ 既往歴(結核歴、がん歴、自己免疫疾患、心不全)
8. 院長からのメッセージ
健診で「胸部異常影」と聞くと不安になりますが、異常影=がんではありません。多くはCTで性状を確認し、過去画像と比較することで、不要な心配を避けられます。私たちは
・見逃さない精査(必要時は当日〜速やかにCT・血液・喀痰検査)
・やり過ぎない検査(低線量CTを基本に、範囲と回数を最小化)
・納得の説明(結果・選択肢・リスクをわかりやすく可視化)
を行っています。検査で胸部レントゲン検査で異常を指摘された場合には、ご相談ください。
当院HPの記事はこちら「CT検査・健診レントゲン異常の精密検査」
参考資料:
日本検診学会 「肺がんCT検診ガイドライン」
https://www.jscts.org/index.php?page=guideline_index
記事作成:

名古屋おもて内科・呼吸器内科クリニック
院長 表紀仁
医学博士・呼吸器内科専門医